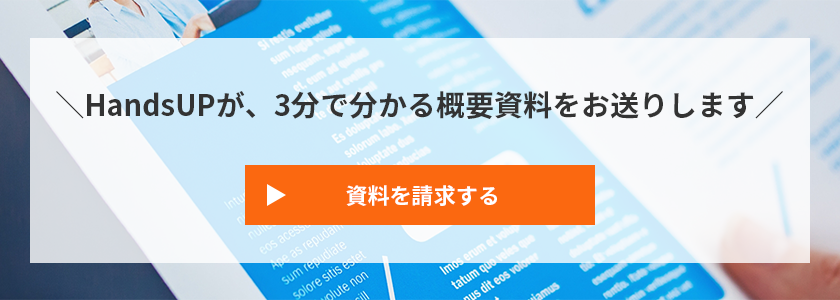越境ECで日本酒は販売できる?必要な免許やおすすめのプラットフォーム、成功事例も解説

和食ブームの影響で、海外でも日本酒への関心が高まっています。そのような日本酒の人気が急上昇する中、越境ECで日本酒を販売しようと考える方も増えていることでしょう。
日本酒を越境ECで販売するためには、各国の規制や法律、輸出に必要な許可を確認することが重要です。
本記事では、越境ECで日本酒を販売する方法、国ごとの規制、そして取得すべき免許について詳しく解説します。
越境ECにおいて日本酒は需要がある?

和食ブームの影響により、海外での日本酒の市場が拡大しています。
財務省が2024年に発表した「最近の日本産酒類の輸出動向について」によると、酒類の輸出額は2021年に急増し、2022年には過去最高額を記録しました。
2023年も前年に次ぐ高い水準を維持しており、酒類輸出額を種類別に見ると、最も高いのはウイスキーで、次いで日本酒が続いています。ウイスキーと日本酒の輸出額は、全体の約68%を占めているほどです。
国別の輸出額では、中国が最も多く、次いでアメリカ、韓国、台湾となっています。韓国と台湾では日本酒の人気が特に高まっており、ウイスキーだけでなく日本酒の需要も増加しています。
海外へお酒を輸出する際は輸出免税が適用されるため注意が必要
日本でお酒を販売する際には、酒税がかかりますが、海外に輸出する場合は免除されます。これは「酒類の輸出免税」が適用されるためです。
国税局や税務署が定める酒類の輸出免税の適用要件は、次のとおりです。
・酒類製造者自らが輸出
・酒類製造者が輸出業者を通じて輸出
また、酒類を輸出する際に免税の適用を受けるためには、所属する税務署に対して「酒税納税申告書」を期限内に提出する必要があります。この申告書には、輸出した酒類の税率区分と数量を記載しなければなりません。
越境ECで日本酒を販売する際に必要な免許

越境ECで日本酒を販売する際に必要となる免許は次の2つです。
・輸出入酒類卸売業免許
・通信販売酒類小売業免許(日本国内でもEC販売をする場合)
越境ECで日本酒を販売するには、「輸出入酒類卸売業免許」を取得する必要があります。
この免許を取得する際、酒類の販売経験は必須ではないため、他業種の企業でも取得は可能です。また、越境ECだけでなく日本国内で日本酒をEC販売する場合は、「通信販売酒類小売業免許」も必要となります。
越境ECで日本酒を販売する際に知っておくべき各国の規制

越境ECで日本酒を販売する場合、国によっては酒類の販売に規制が設けられています。販売する国の規制を事前に確認し、適切な対応をしなければ、重い罰則が科せられるおそれがあるため注意が必要です。
ここでは、酒類販売における各国の規制について解説します。
フランス・イギリス・ドイツなどのヨーロッパ諸国
フランスとイギリスでは、消費者保護の観点から、14日間のクーリングオフ制度が設けられています。これにより、購入者は商品を受け取ってから14日以内であれば、理由を問わず注文をキャンセルすることが可能です。
さらに、販売者は購入者に対して注文から30日以内に商品を届ける義務があります。ただし、購入者が「誕生日に合わせて届けてほしい」などの理由で注文後31日以降の配達を希望する場合は例外です。
また、フランスで越境ECを利用して日本酒を販売する場合、「アルコール販売ライセンス」の取得が必要となります。
ドイツでは、有機食品を販売する際にドイツの認可と登録が必要です。日本酒と一緒に日本で製造されたオーガニックワインも販売する場合は、事前に必要な認可と登録をおこないましょう。
韓国・中国などのアジア諸国
中国では、2018年以降、ビールの越境EC販売が禁止されています。一方で、日本酒や梅酒の販売は可能です。ただし、日本酒と一緒に日本国内で製造されるご当地ビールを販売することは違法となるため、注意しましょう。
また、2011年の福島第一原発事故の影響で、福島、群馬、新潟、東京を含む10都県産の食料品は中国への輸出が禁止されています。そのため、たとえ中国で販売が許可されている日本酒であっても、これらの都県産のものは越境ECで販売できません。
韓国においては、酒類の流通にさまざまな規制があります。スーパーや専門店、オンラインショップなどの販売チャネルごとに免許制度が設けられており、例えば酒類輸入業免許しか持っていない業者は酒類小売業をおこなうことができません。
そのため、韓国で日本酒を販売するには、まず自ら酒類輸入業免許を取得し、そのうえで韓国の小売販売業者と契約を結んで、消費者に届ける流通経路を確保する必要があります。
越境ECでの日本酒販売におすすめのプラットフォーム4選

越境ECで日本酒を販売する際には、自社でECサイトを立ち上げるよりもプラットフォームを利用するほうが手軽かつ便利です。
ここでは、日本酒を含む酒類全般の販売に適したプラットフォームを紹介します。
天猫
天猫(ティエンマオ)は、中国最大級のEコマース企業であるアリババグループが運営するBtoC型のECサイトです。出品者はアリババに登録手数料を支払うことで、商品を天猫に出品できます。現在、国内外を合わせて約5万点の商品が天猫に出店されています。
天猫で販売されている日本製品の多くは、化粧品やベビー用品です。食品の取り扱いは少なく、日本酒の販売も可能ですが、大きな売上を上げるには工夫が必要でしょう。
京東(JD)
京東(JD)は、中国国内で第2位のシェアを誇るECサイトです。このプラットフォームはAmazonのようなスタイルを採用しています。2015年には、日本製品を専門に扱う「日本館」というサイトも開設されました。
この日本専用サイトの開設背景には、日本製品の販売額が増加していることがあります。京東(JD)では、月桂冠、獺祭、山崎ウイスキーなど、日本でお馴染みのお酒も販売されています。
Cdiscount
Cdiscountは、フランスで最大のECモールで、国内の売上高ではAmazonに次いで2位にランクインしています。
1998年に設立されたCdiscountは、2000年2月にフランスの大手企業であるカジノ・グループの子会社となりました。これにより、それまでの小売業からオンラインマーケットプレイスへと大きく転換しています。
その後、Cdiscountはベルギー、ドイツ、イタリアなどにも事業を拡大し、国際的なECモールとして成長しています。
日本国内からも、月額のストア手数料と商品ごとの販売手数料を支払うことで、Cdiscountに商品を販売・出品することが可能です。
Japan Centre(ジャパンセンター)
Japan Centre(ジャパンセンター)は、1976年に日本人によってイギリスで設立された、日本からの輸入品を取り扱う専門店です。
Japan Centreは、イギリスの顧客に高品質な日本製品を提供するため、食品事業にも進出しています。2011年にはウェストフィールド・ストラトフォード・シティに、2018年にはウェストフィールド・ロンドンにフードホールをオープンし、事業を拡大。また、日本の漫画や生活必需品に加えて、日本酒も取り扱っているため、越境ECで日本酒を販売するのにぴったりなプラットフォームです。
越境ECで日本酒を販売して成功したケース

越境ECで日本酒を販売する際の免許・規制・プラットフォームについて確認してきましたが、実際に事業が成功するのか不安な方も多いでしょう。
ここでは、実際に越境ECでの日本酒販売に成功した事例を2つ紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
日本酒を動画で紹介して販売した事例
ある日本の企業が中国で日本酒を販売する際、中国のSNSを活用してPR動画を制作しました。この動画には、酒蔵の歴史や伝統、製造方法が盛り込まれており、その結果、多くの顧客を獲得することに成功しています。
文字だけでは歴史や伝統、製造方法を理解するのが難しく、消費者の印象にも残りにくいというデメリットがあります。しかし、動画は視覚的に訴える力が強いため、心に響きやすく、購買意欲の向上につながりやすいです。
さらに、中国で影響力のあるインフルエンサーと協力することで、酒類にあまり興味のなかったユーザーからも注目を集めることができ、越境ECにおける日本酒販売の成功率をさらに高めることが期待できます。
日本酒に特化した越境ECサイトを利用した事例
日本酒専門の越境ECサイトを利用することも、成功率を上げるための一つの方法です。
ある日本企業は酒造メーカーと協力し、日本酒専用の越境ECサイトを立ち上げて販売を開始しました。
このサイトでは、さまざまな酒造会社の日本酒を検索できる機能や、酒造から直接発送される点が評価され、各国の消費者から支持を得ています。
産地直送により、新鮮さをアピールしつつ、安心感を提供している成功事例です。
越境ECで日本酒を販売する際は事前調査に力を入れよう

世界各国で日本酒の人気が高まっており、海外で日本酒を購入したいと考える消費者が増えています。越境ECを利用すれば、日本酒を手軽に販売できると考える方も多いでしょう。
しかし、日本酒を海外で販売するには、各国の規制や免許の確認が必要です。また、その国に適したPR方法を考える必要もあります。
17LIVEでは、販売から物流までの工程を一括で対応できる越境コマース支援を提供しています。見積もりやご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。